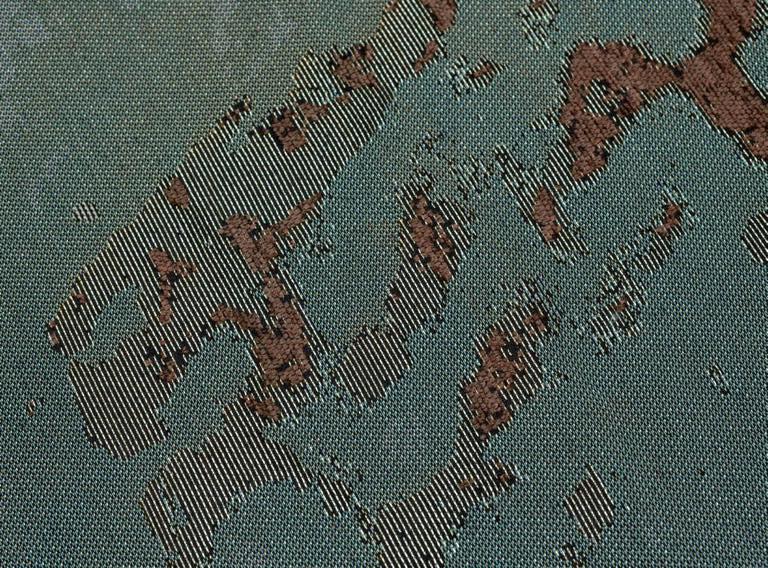世界は果てしなく大きく、天も広大無辺だ。 すべてを眼で捉えなければならないとすれば、とてもすべてに考えがおよばない。
ヨハン・ヴォルフガンク・フォン・ゲーテ「ハワードの雲形論への三部曲」より
ムン・キョンウォンは、「プロミス・パーク・プロジェクト(以下PPP)の制作過程において、かなり早い段階から「絨毯」に注目する発言を行っていた。「公園」は一般的に、非常に固定的なものであり、可変的ではないし、もちろん基本的には移動可能ではない。それに対し、アーティストが、公園は時間的な存在なのか、空間的多様性は獲得可能なのか、といった問いを投げかけることは可能であるし、そうしないことには、「公園」の新たな相貌や未来的な可能性は垣間見えてはこない。
ムンが「PPP」の他に、別に進行するプロジェクトとも並行して共通して注目する概念に「縮地」Shukuchi/Folding Spaceがある。「縮地」とは、神仙思想の中で登場する仙術の一つで、空間を折り畳んで距離を圧縮し、遠方まで一気に瞬間移動で到達する、あるいは見通す能力のことを言う。中国晋代の『神仙伝』に登場する方士費長房(ひちょうぼう)の故事に由来する概念で、実は朝鮮半島にも古くからこの概念が伝わり、使用されていたと言われている。実際、「縮地」は想像上の手段であり、哲学的思考操作であると思われるが、説話的なイメージ化を行うとき、神仙思想の仙人は、土地と土地を飛び越える一瞬のワーピング、すなわちテレポーテーションのために、補完的な要素として身体を搭乗させるヴィークルが必要になる。そして、東アジアでは雲が実体的な搭乗メディアになり、アラビアでは空中を浮遊する絨毯に乗るといったイメージに行き着くのである。
テレポーテーションの具体化は、19世紀末に電話が生まれ、飛行船が開発され、そしてアニメーションや映画が発展することで、このような縮地とヴィークルの関係の実体化したイメージは一般的なものとなった。(量子論の発展の先には具体的な物体のテレポーテーションも現実化するかもしれない。)しかし、人間の記憶量を遥かに凌駕する電子情報がネットワーク上で瞬時にやり取りされる現在、むしろヴィークルの支持体的イメージは不要であり、ここで「縮地」が必要とされるのは、電子空間の増大し続ける膨大なデータベースに人間が対峙する場合に必然となってくるデータマイニングやデータビジュアリゼーションといった、データスケープの情報の抽象化と跳躍や圧縮である。データとはフィルタリングされた人工物であるが、その多領域にわたる膨大な量に直面する時点で適切なビジュアリゼーションを発動させ得なければ、人間にとって有意性の無いただの塊やうねりのようなものにすぎない。「縮地」とは過去においては、空間的あるいは時間的延長への挑戦と想像であり、現在の情報化社会では、それが変質してデータビジュアリゼーションとなるが、いずれにしても人間の知覚と思考にとっての必然的な、移動・圧縮・抽象(・あるいは翻訳)なのである。
フリードリヒ・キットラーは「テクストと楽譜。ヨーロッパにはこれ以外に時間の記憶法がなかった。そして双方の根拠を形づくっているのは文字というものであり、文字の時間はサンボリックな時間であった。この時間は先行したり遡行したりすることが可能であり、それを繰り返しながら、まるでいくつかの鎖からひとつの鎖をたぐるようにして、みずからを記憶してゆく。それに対して物理的な平面、あるいはリアルなものの平面で時間として流れているものは盲目であり、予見不可能であって、これをコード化することは絶対にできない。」と書く。「文字(アルファベット)の独裁。」しかし、はたしてそうだろうか。人間の有史以来において、文字以外に、先行や遡行可能な物理的なメディアは存在しないのだろうか。文字に並行して、時間を補完できるメディアは情報化社会以前には存在しないのだろうか。「PPP」では、ブリコラージュの進化としての織物による絨毯(無地の絨毯というものは近代以前には存在しないのではないか?)に注目し、絨毯の保持している表象と文様の存在意義に、「縮地」の作用、すなわち単層的なフィギュラティブなゲシュタルトではなく、先行や遡行の時間性のコードの読み取りを可能とするフィギュラルな可能性、を見いだそうとする。さらには「縮地」が含意する、身体性と浮遊というイメージも別な形で重要度を持ってくる。
絨毯は、中央アジア地方、つまり東洋起源の床や壁を覆う織物が祖元である。最古の事例は紀元前5世紀のものとされ、11世紀の十字軍のトルコ遠征時に西ヨーロッパにもたらされた。その後のヨーロッパ中世では、壁掛け織物であるタピストリーが流行し、大型の画像を織り込む技術が発達し、ルネサンス時代以降は著名な絵画のマルチプル化が可能な複製技術品としての役割を担った。それらは写真以前の手工業的複製メディアでありオリジナルの意味を多様化するシミュラークルでもある。しかもそれらは物理的にもポータブルなヴィークルであった。ジョゼフ・L・マンキーウィッツ監督の映画「クレオパトラ」(1963)では、エリザベス・テイラー演じるクレオパトラは、秘密の通路を経由して、絨毯に巻かれた形でシーザーの前に現れる。棒状に巻かれた絨毯が広げられるとクレオパトラがその中から登上するという具合だ。
絨毯にさらなる意味と発想を付け加えたのはミシェル・フーコーである。フーコーは有名なラジオ講演「ヘテロトピア」(1966)の中で、東洋の絨毯が庭園を模倣しており、加えて絨毯を「移動する庭園」、ポータブルなヴィークルとして捉え、それこそがユートピアへと繋がるものであるという見解を示した。「…東洋の絨毯がもともとは庭園(温室=冬の庭園)を模したものであったことを考えるなら、空飛ぶ絨毯の世界を踏破した伝説的価値を理解することができる。庭園とは、世界全体がその象徴的な完成をそこに成し遂げにやってくるような絨毯なのであり、絨毯とは、空間を横切るような動く庭園なのである。…世界の美のすべてがこの鏡に集められていることがわかる。庭園とは、古代の基層以来、一つのユートピアの場所なのである。…」フーコーの外の思考においては、ヘテロトピアはユートピアと相反する概念である。なぜ相反するのかといえば、ユートピアは非現実的な存在であるが、ヘテロトピアは、非身体的、非場所的な他の存在であるが現実的なものであるという。それは「実際のところ、私の身体はつねによそにあり、それは世界のすべてのよそに結びついている」のである。このよそ=他への移行のイメージとしてフーコーは鏡や船を例えるが、それらは視覚的なヴィークルであり、絨毯もそのようなメディアとして捉えられている。庭園を、都市の延長との関係ではなく、ある種の身体との関係から考察した時、庭園自体の空間構造や機能を逸脱し、庭園と身体の特異性のみが非場所性を志向する意味で、庭園は絨毯と等位になる。そして場所性の移行やネットワークを可能にし、本質的なユートピア性に到達するための装置となりうるのではないか。PPPのインスタレーションの2つの絨毯とは、その二重の意味での非場所への移行を示しているのであろう。
絨毯の織り技術は、多様な繊維、表象、層構造が、2次元平面に一体に組み合わされる組織的潜在性を有し、織りの複雑性は身体感覚的、光学的に還元されることで空間のモルフォシスに生まれ変わる。「PPP」では、17m X 17mの壮大なスケールの絨毯を京都西陣織とのコラボレーションを経て制作した。そこでは、2次元的床面に対して、8層のイメージを3次元的な奥行きとして、特別な技法とデジタルソフトウェアを用いて織り込むことを実現した。絨毯のイメージは、リサーチをおこなった公園や近代産業遺構の膨大なドローン撮影データから、ブリコラージュ的に組み合わされたイメージが使用され、それを西陣織のシステムに翻訳置換し織り上げられた。それによって壮大な布地は、新たな細部を多様に有した複雑な床面を生み出すことになった。ムンは、絨毯の床面文様を人類史的視点から捉え、それを生成するアーカイヴと発想しているのである。
ムンは2013年の段階から、実写においてもCGにおいても無人の風景を選び、植物による緑化増殖が人工的な都市を徐々に変化させていくイメージを維持してきた。近代公園の成立と植物の繋がりはまた興味深い関係を喚び起こしてくれる。1851年公開の世界最初の公共公園であるハイドパークにおいて開催された第1回万国博覧会では、鉄骨とガラスの巨大なパビリオン、クリスタルパレスが設営されたが、イギリスの建築家のオーウェン・ジョーンズは、クリスタルパレスの外装と内部展示物の装飾を手がけるために、古今東西の装飾文様を調査し体系化をおこない、それが数年後に『装飾の文法』(1856)に集大成化される。これによって、従来人間世界や神話世界の代理表象であった美術の中に、デザインの独立した意味を見出す最初の事例であり、植物をベースにした装飾文様自体の自立的価値が認識された一つの画期と言えるだろう。さらにその数十年後、美術史家アロイス・リーグルは、装飾要素の自律的な空間増殖と対象の持つ視覚性と触覚性の遠近法的関係との相関関係に注目して、形式に対する芸術作品(特に工芸と装飾)が内在させている「芸術意志」を提唱したことも明記しておくべきだろう。
近未来においては、現実的な空間延長を持たない電子公園がはたして可能になるだろうか。そこでは、身体と公園という関係性のフレーム、移動という行為がどのように捉え直されるのだろうか。さらに重要になるのは、カオス的に自己増殖する植物や文様のような存在をどのように非制御的にコード化するかである。非表象的な存在であるバイオテクノロジーへの接近も電子公園にとって興味深い要素である。